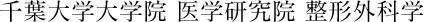42nd Annual PAMA International Symposium(英国)および第11回日本舞台医学会学術集会(奈良)参加報告
更新日 2025.4.3
ご報告が遅くなりましたが、2024年7月18日-21日に英国ロンドンにあるUniversity College London(UCL)で開催された42nd Annual PAMA International Symposiumで口演いたしました。演題名は、Group medical examination of professional pianists’ hands by medical team in Japan(Aya Kanazuka, Ryutaro Iwasaki, Yusuke Matsuura, Noriko Ogawa, Katsunori Ishii, Seiji Ohtori)で、東京音大での上肢メディカルチェックの結果を報告いたしました。
東京音大との連携は、大鳥精司先生、松浦佑介先生のご協力のもと2022年から開始しております。メディカルチェック当日は、東京音大の小川典子先生、石井克典先生のご尽力で現場のマネージメントを行なっていただき、また手外科グループの大学院生や医学生、当院および関連病院のリハ部作業療法士にも実務を担当していただいております。このような取り組みはPAM先進国である欧米でも珍しいようで、今後も学術的な発信を継続したいと思っております。
開催地であるUCLは私の卒業校であり、かつての恩師と再会できる機会となり、大変懐かしく思いました。特にHara Trouli先生(整形外科医)は、第10回日本舞台医学会学術集会(札幌医大)でWeb講演を快諾いただき、貴重なPAM医療従事者育成のプログラム内容についてお話いただくなど、交流が継続しております。また、Hand TherapistのKatherine Butler先生とは帰国後も症例相談などで時折お世話になっております。当院のPAM外来には、海外で活動されている音楽家の方も来院されるため、現地でPAM診療を行える医師の情報のアップデートも必要であり、国際的な連携が重要と認識しております。
また、2025年3月8日(土)に奈良春日野国際フォーラム 甍 ~I・RA・KA~にて開催された第11回日本舞台医学会学術集会(https://naraseikei.com/stagemedicine2025/index.html)
のシンポジウムにて口演の機会をいただきました。演題名は「音楽大学での講義や上肢メディカルチェックで見えてきたこと」で、上述のPAMAの内容に、医学生や若手医師、PAMに興味のある医療従事者向けの内容を加えました。
当院リハビリテーション部の作業療法士 近藤敬一先生には、「音楽大学ピアノ科教員への演奏前ウォームアップに関するワークショップの取組み(続報)」としてご発表いただきました。音大での調査により、演奏家は身体的なWarming-up/Cool-down exerciseの必要性を認識しているものの、スポーツアスリートと比較してその実施率が著しく低いことがわかりました。私たちは、英国PAM学会推奨のプログラムを基盤に、楽器特異的な姿勢や運動、特定の疾病の対策を意識したメニューを追加した「簡単10分でできる身体的ウォームアップ」を立案し、これをメディカルチェック時の待ち時間を利用したワークショップで紹介しております。今後も発信を継続して参ります。
また、日常診療でPAMリハに関して連携させていただいております船橋整形外科クリニックの作業療法士 草木妙子先生にも、舞台医学に興味のある医療従事者向けのシンポジウムで、シンポジストへの質問者としてご登壇いただきました。さらに、今回学会終了後の交流会では、演奏家のフォーカルジストニア診療でお世話になりました脳神経内科の和泉未知子先生に素敵なギター演奏と歌をご披露いただきました。専門の枠を超えて、音楽好きという共通項でつながる友情に心温まる思いがするとともに、少しずつ仲間が増えていることを嬉しく思っております。
また、最近の取り組みとして、PAMに興味のある作業療法士の先生を対象として、先述のKatherine Butler先生のPAMリハの指南書を読み合わせるWeb勉強会を月1回のペースで開始しました。私自身勉強になることも多く、楽しく開催しております。このような機会の積み重ねを通じ、PAM診療の充実を目指しております。
日頃お世話になっております鈴木 崇根先生、松浦佑介先生、赤坂 朋代先生、山崎貴弘先生、手外科グループおよび臨床試験部の皆様、また仕事を理解し育児を分業しサポートしてくれている家族には改めて感謝を申し上げます。PAMを目指す若手医学生や整形外科医を増やしたいという思いが常にある中、自身の研鑽、日常業務、研究活動のバランスは難しく、均衡を保とうとすると遅々として進まない日もあります。しかしながらこうしてPAMの診療や学術活動を継続できるのもこうした様々な応援があってのことであり、これからも尽力したいと思います。